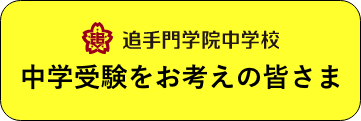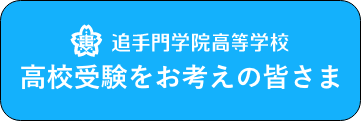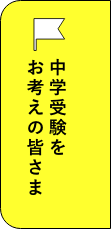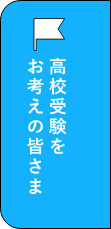食堂の前にクチナシの花が咲き始めました。例年通り、花の存在に気づくよりも先に、クチナシの花の甘い香りが漂ってきました。沈丁花とか金木犀とかも同じように、花よりも香りの方が主張しますね。香りとか匂いは人間の記憶と結びつきやすいようで、私は沈丁花の香りを嗅ぐと、幼少期を過ごした家の庭の様子を思い出しますし、金木犀の花の香りに気づくと、教員としての青春時代に生徒と共に取り組んだ体育祭や文化祭のことを思い出します。
フランスの小説家、マルセル・プルーストが書いた『失われた時を求めて』という長編小説の中で、紅茶の中に入っていたプチット・マドレーヌの欠片を口に含んだとたんに、突然の幸福感に満たされ、様々な記憶が蘇ってくるということが描かれています。
コンブレーにかんして、就寝の悲劇とその舞台以外のものがすべて私にとって存在しなくなってから、すでに長い歳月が経っていたが、ある冬の日、帰宅した私が凍えているのを見た母が、私の習慣に反して、紅茶を少し飲んでみてはと勧めてくれた。最初は断ったものの、なぜか思い直して飲んでみることにした。そこで母が持って来させたのは、溝のあるホタテ貝の殻に入れて焼きあげたような「プチット・マドレーヌ」という小ぶりのふっくらとしたお菓子だった。やがて私は、その日が陰鬱で、明日も陰気だろうという思いに気を滅入らせつつ、なにげなく紅茶を一さじすくって唇に運んだが、そのなかに柔らかくなったひとかけらのマドレーヌがまじっていた。ところがお菓子のかけらのまじったひと口が口蓋にふれたとたん、私は身震いし、内部で尋常ならざることがおこっているのに気づいた。えもいわれる快感が私のなかに入りこみ、それだけがぽつんと存在して原因はわからないその快感のおかげで、たちまち私には人生の有為転変などどうでもよくなり、人生の災禍も無害なものに感じられ、人生の短さも錯覚に思えたが、それは恋心の作用と同じで、私自身が貴重なエッセンスで充たされていたからである。
『失われた時を求めて1 スワン家のほうへⅠ』マルセル・プルースト・作 吉川一義・訳 岩波文庫
岩波文庫で全13巻という、とてつもなく長い小説で、読み始めても最後まで読み終えることがなかなかできない小説です。私は大学時代に3か月くらいかけて読み終えました。この小説のこの部分をもとに、匂いとか風味が、様々な記憶と結びつくということを「プルースト効果」と呼ぶそうですが、確かにそういうことがあるように思います。手ごわい相手ですが、よろしければ、『失われた時を求めて』にチャレンジしてみてください。